学部教員のキーワードごとの研究紹介
キーワード
<生態系・進化>

荒西 太士 教授(生命科学科)
特殊な閉鎖性水域であるダム湖において特定外来種による生態系攪乱リスクを評価しています。
![]()
![]()
![]()
![]()

児玉 有紀 教授(生命科学科)
繊毛虫のミドリゾウリムシとその細胞内に共生しているクロレラを使って,細胞内共生の成立の仕組みを研究することにより,真核細胞の誕生や進化の過程の解明を目指しています。
![]()
![]()
![]()

高原 輝彦 教授(生命科学科)
生き物たちからこぼれ落ちた環境中のDNAやRNAの情報を手がかりにして,山陰の湖沼・河川・海などにおける未知なる生態系の解明と生態系サービスの再発見・利活用を目指しています。
![]()
![]()
![]()

広橋 教貴 教授(生命科学科)
自然界で観察困難な現象の1つに深海生物の繁殖があります。私たちは遺伝子解析技術を用いて深海性イカ類の独特な繁殖様式を調査し,海洋生態系の理解を深めようとしています。
![]()
![]()

舞木 昭彦 准教授(生命科学科)
生態系はいかに進化し・維持されているのでしょう。前者の謎はダーウィンが基本的に解きましたが,後者の謎は未解明です。そこで数学の力を使い生態系の維持方法を研究しています。
![]()
![]()
![]()

古水 千尋 准教授(生命科学科)
陸上植物の多様な形態や微生物との相互作用が進化する仕組みを、ペプチドホルモンを手がかりに研究しています。
https://www.ipc.shimane-u.ac.jp/evobio/
![]()
![]()
![]()

須貝 杏子 助教(生命科学科)
「島」は外からの移入が制限された生態系です。島に辿り着いた植物種が多様化する仕組みを野外調査と遺伝解析で明らかにしています。
![]()

山口 陽子 助教(生命科学科)
体内の恒常性を維持するしくみの起源・進化について,マイナーな魚類(ヌタウナギ)を使って研究しています。
![]()

大沼 耕平 助教(生命科学科)
ホヤと巻貝の胚を用いて、受精卵から神経系が作られる仕組みとその仕組みの進化・多様性を調べています。
![]()
![]()

宮永 龍一 教授(環境共生科学科)
ハナバチ類の生態について研究を行っています。ハナバチは生態系サービスのひとつ「送粉」の主要な担い手です。作物の生産や被子植物の繁殖にハナバチがどのように寄与しているのか,フィールド調査を中心に研究を行っています。
![]()

山口 啓子 教授(環境共生科学科)
水生生物は環境の良い指標となります。二枚貝をはじめとした水生生物の生態,特に環境との関係,貝殻や耳石などの硬組織から生息環境履歴を読み取る研究をしています。
![]()
![]()

久保 満佐子 准教授(環境共生科学科)
火入れや草刈り等で維持されてきた草原生態系には稀少な植物が多く生育しています。こうした植物の生態や保全に関する研究を行っています。
![]()

倉田 健悟 准教授(環境共生科学科)
宍道湖や中海などの汽水域生態系の生物群集(二枚貝類,甲殻類等の底生生物)と人為的影響(気候変動,河川改修等)に関する研究を行っています。
http://www.ess.shimane-u.ac.jp/kengo/
![]()

清水 加耶 助教(環境共生科学科)
東南アジアの熱帯雨林に生息する昆虫が植物や他の動物類とどのように関わりながら群集を構成しているのかを研究しています。
![]()

林 昌平 助教(環境共生科学科)
南極の土砂にはどのような微生物が生息しているのか,また,その微生物から医薬品や農薬のもととなる活性物質が見つからないかを調査しています。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

吉田 真明 教授(附属生物資源教育研究センター)
海洋生物はそれぞれの好む環境にどのように適応しているのか,ゲノムDNAを調べてその進化を解き明かす研究を行っています。
![]()
![]()
![]()
![]()

小野 廣記 助教(附属生物資源教育研究センター)
頭足類(イカやタコ)などの海洋生物を用いて,そのユニークな姿かたちがどのように進化してきたのか,胚発生・遺伝的側面から研究をしています。
![]()
![]()
![]()
<生体応答・環境応答>

赤間 一仁 教授(生命科学科)
ゲノム編集技術を用いてGABAを増量したイネを開発し,様々な環境ストレスに対する耐性試験を進めています。
![]()
![]()

荒西 太士 教授(生命科学科)
汽水性の河川湖沼で異常繁茂している水草藻類の経年変動を観測して防除方法を検討しています。
![]()
![]()
![]()
![]()

石川 孝博 教授(生命科学科)
植物はビタミンC(アスコルビン酸)を豊富に含んでいますが,どうやって?なんのために?たくさん生産するのか,モデル植物を使って解明を進めています。
![]()
![]()
![]()

塩月 孝博 教授(生命科学科)
昆虫に特有な脱皮変態は昆虫ホルモンの作用により起こるので,その調節の仕組みを調べるとともに,それを人為的にコントロールする方法を探索しています。
![]()
![]()

清水 英寿 教授(生命科学科)
湖沼の富栄養化に伴い発生するアオコが産生する毒素が,どのようなメカニズムを介して体の不調(臓器機能低下)を導くのか解析を行なっています。
![]()

丸田 隆典 教授(生命科学科)
変動環境下における植物の生死決定の分子機構の解明を目的として,ビタミンCと酸化ストレスの関係性について調べています。
![]()
![]()
![]()
![]()

松尾 安浩 教授(生命科学科)
分裂酵母をモデル生物として,グルコース飢餓状態での細胞周期制御に及ぼす影響とそのメカニズムを解析し,病気との関連性を調べています。
![]()
![]()

池田 泉 准教授(生命科学科)
生物制御剤の作用点となる神経伝達物質受容体を標的として合成した種々の新規化合物を用いて,その受容体の薬物結合部位の詳細を解明する研究を行っています。
![]()
![]()
![]()

石田 秀樹 准教授(生命科学科)
単細胞の原生生物が外傷によって核を含む細胞の半分を失っても,元の形態にまで再生できたり新たな分裂が可能となるメカニズムについて研究を進めています。
![]()
![]()
![]()

小川 貴央 准教授(生命科学科)
植物における補酵素型ビタミンB(NADやFAD)の代謝調節機構と,それらの蓄積量の変化が植物の生育や環境応答などに及ぼす影響について研究を進めています。
![]()
![]()
![]()

地阪 光生 准教授(生命科学科)
多価不飽和脂肪酸から種々のホルモン様物質を作り出すために重要な酸素添加反応を触媒する酵素の構造と機能を解明し,生体応答の仕組みや制御方法の開拓を目指しています。
![]()
![]()

西村 浩二 准教授(生命科学科)
環境変化や病原体の攻撃に応答する仕組みを蛍光バイオイメージングで細胞・個体レベルで解析し,環境ストレスや病原体の攻撃に頑強な適応機構を持つ農作物の創出を目指す研究を進めています。
![]()
![]()
![]()

古水 千尋 准教授(生命科学科)
陸上植物の多様な形態や微生物との相互作用が進化する仕組みを、ペプチドホルモンを手がかりに研究しています。
https://www.ipc.shimane-u.ac.jp/evobio/
![]()
![]()
![]()
![]()

秋廣 高志 助教(生命科学科)
ストレス耐性作物の開発。シロイヌナズナの膜輸送体を解析し,塩害や病害虫に強い作物を育成する研究を行っています。
![]()
![]()

山口 陽子 助教(生命科学科)
地球温暖化が生物の生理・生態にどのように影響するか,海洋スカベンジャ―であるヌタウナギで調べています。
![]()
![]()

大沼 耕平 助教(生命科学科)
ホヤ幼生の光や重力への応答に必要な神経ネットワークを同定し、さらにその発生や詳細な動作の仕組みを追究します。
![]()
![]()

加古 哲也 助教(農林生産学科)
植物の気温や光等の環境条件に対する応答を利用した生産・流通技術について研究を行っています。
![]()
![]()

谷野 章 教授(環境共生科学科)
太陽電池パネルの下で植物がどのように育つかについて研究しています。気候変動,食料と人口の偏在,エネルギー資源転換が一斉に進行するためにこのような研究が必要です。
![]()

泉 洋平 准教授(環境共生科学科)
昆虫の低温耐性,特に凍結耐性について,昆虫体内でどのような物質が生産され,それがどのような役割を持っているのかについて研究しています。
![]()
![]()

劉 佳啓 准教授(環境共生科学科)
レキ(礫)や植物被覆が飛砂の発生に及ぼす影響を風洞実験で解析し、植生や地表特性の違いによる環境応答のメカニズム解明に取り組んでいます。
![]()
![]()
![]()
![]()

林 昌平 助教(環境共生科学科)
アオコやカビ臭の原因生物であるシアノバクテリアの増殖を引き起こす環境要因を特定し,どのようにダムを管理すれば水資源を適切に運用できるかを調査しています。
![]()
![]()
<食品機能・栄養・健康>

清水 英寿 教授(生命科学科)
食したタンパク質を起因として腸内細菌によって産生される化合物が,健康増進や疾患の発症・進展にどのような影響を及ぼすのか研究を進めています。
![]()

室田 佳恵子 教授(生命科学科)
食品成分の生体利用性について研究しています。特に,食事性脂質のより健康的な摂取方法や,ポリフェノールなどの機能性成分の吸収代謝機構と生理作用の関係に着目しています。
![]()
![]()

山本 達之 教授(生命科学科)
光と分子の相互作用によって,分子の性質や環境を調べる「分子分光学」の研究を行っています。この手法の一つ,ラマン分光法によって,生きた細胞をあるがままに調べたり,病気の新しい診断法の開発を目指しています。
![]()

松尾 安浩 教授(生命科学科)
日本酒やビールを生産するには,酵母によるアルコール発酵が重要です。そこで,島根県内でビール酵母の単離と特徴的な香りを生産する清酒酵母の開発を行っています。
![]()
![]()
![]()

吉清 恵介 教授(生命科学科)
シクロデキストリン(分子カプセル)でエゴマ油を粉末化し,効率的に体内のオメガ3系脂肪酸を増加させる研究をしています。
![]()

戒能 智宏 准教授(生命科学科)
分裂酵母を用いて,電子伝達系でのエネルギー生産に関与し,抗酸化能を有するコエンザイムQ(ユビキノン)の合成酵素遺伝子や細胞内での生理機能の研究を行っています。
![]()

地阪 光生 准教授(生命科学科)
乳酸菌の代謝力を引き出し活用して,食品の機能性成分となる低吸収性の配糖体を高吸収性代謝物に変換することにより,食品の機能性を強化する研究を進めています。
![]()
![]()

西村 浩二 准教授(生命科学科)
私たちのからだに良い健康成分を植物細胞の中にたくさん溜め込む仕組みを開発し,機能性に優れた付加価値の高い農作物を創出させる研究を進めています。
![]()
![]()
![]()

Hemanth Nag Noothalapati Venkata(ヌータラパティ ヘマンス) 准教授(生命科学科)
分光スペクトルをAIを用いて解析しています。主にラマン分光法という手法を用いて,医学,生物学,食品,環境等の幅広い分野において,分光法とAI技術が融合した新しい応用研究を進めています。
![]()

小林 伸雄 教授(農林生産学科)
良食味で高い食品機能性成分を含有し,見た目も美しいダイコンやナバナの品種改良に関する研究を行っています。
![]()
![]()

池浦 博美 准教授(農林生産学科)
園芸植物に含まれる健康に資する成分が,生育や加工によってどのような変化が起きるのかについての研究を行っています。
![]()

田中 秀幸 准教授(農林生産学科)
施設園芸において,光や肥料を制御した栽培管理によりトマトの機能成分であるリコピン含量がどのように変化するかについて研究を行っています。
![]()

足立 文彦 助教(農林生産学科)
植物のアレロパシーを利用したダイズへの根粒菌の着生促進とダイズ子実の機能性成分の向上を研究しています。
![]()

宋 相憲 助教(農林生産学科)
ミールワームの消化器官内に定着している有用な微生物を特定し,難消化性物質の分解や,機能性成分の活性化,食品加工副産物などの利用性向上に活用する研究を行います。
![]()
![]()
![]()
![]()
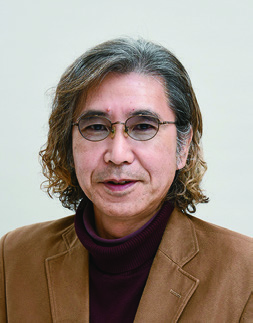
松本 眞悟 教授(附属生物資源教育研究センター)
島根県産の朝鮮人参は雲州人参と呼ばれ,本場韓国産と並び最も成分品質が高いと言われています。本研究室では伝統的な栽培方法に代わる新たな雲州人参栽培技術の確立に取り組んでいます。
![]()
![]()
![]()

児玉 基一朗 特任教授(先鋭研究部門)
未利用地域資源であるニホンナシ葉に含まれる機能性ポリフェノール類(ナシポリフェノール)を活用した、食品(お茶、スイーツなど)や化粧品を開発しています。
![]()
![]()
![]()
<食料生産>

荒西 太士 教授(生命科学科)
有用水産資源であるアユやアオデなどの遺伝構造を解析して持続的な再生産を管理しています。
![]()
![]()
![]()
![]()

石川 孝博 教授(生命科学科)
ゲノム編集など最新の技術をつかって,微細藻類ユーグレナ(和名:ミドリムシ)の代謝を改変し,脂質・糖・ビタミンなど有用物質の生産性を増大する研究に取組んでいます。係に着目しています。
![]()
![]()
![]()
![]()

丸田 隆典 教授(生命科学科)
食糧の安定供給や栄養価の向上を目指して,ストレス耐性能力や栄養素の生産能力を高めた植物開発に取り組んでいます。
![]()
![]()
![]()
![]()

古水 千尋 准教授(生命科学科)
植物の環境応答の仕組みを研究し、その理解を作物の生産性向上につなげることを目指しています。
https://www.ipc.shimane-u.ac.jp/evobio/
![]()
![]()
![]()
![]()

一戸 俊義 教授(農林生産学科)
島根県島嶼(知夫村),島根県中央部(邑智郡)における和牛生産システムについて検討しています。主に,地域資源の活用方法,周年放牧でのエネルギー利用,県ブランド牛の肥育について研究しています。
![]()
![]()
![]()

江角 智也 教授(農林生産学科)
カキやブドウの果樹の成長や開花,果実発達にまつわる不思議を解明して,果物の新品種や地域特産品を開発します。
突然変異育種でアズキの変わり種を見つけ,和菓子やぜんざいで使う出雲地方オリジナルアズキを作ります。
![]()
![]()
![]()

松本 敏一 教授(農林生産学科)
LED補光やバイオスティミュラント処理等によるブドウの着色促進,糖度上昇を目指した研究を行っています。
![]()

氏家 和広 准教授(農林生産学科)
機能性食品素材として注目されているキノア(キヌア)について,安定的に栽培する方法の検討や日本の風土に合った新品種の育成を目指した研究を行っています。
地球温暖化の影響により,コメが白く濁って品質が低下してしまう白未熟粒の問題が深刻化しています。この現象の原因究明と対応策の検討に取り組んでいます。
![]()
![]()

門脇 正行 准教授(農林生産学科)
サツマイモの安定的に効率良く生産するための方法を研究しています。7月の茎葉の繁茂程度から10月に収穫できるイモの量を予測しようと試みています。
![]()
![]()

小林 和広 准教授(農林生産学科)
地球温暖化の進行で危険性が大きくなる,高温が水稲生産に及ぼす影響を明らかにし,その対策を研究しています。
https://www.ipc.shimane-u.ac.jp/food/kobayasi/
![]()
![]()

田中 秀幸 准教授(農林生産学科)
ミニトマトの収量増加のため,植物ホルモンの一種であるサイトカイニンに着目し,その生合成量の制御が花数に及ぼす影響を調査しています。
![]()
![]()

足立 文彦 助教(農林生産学科)
サツマイモの食味・食感と品種・土壌条件・気象条件との関係を調べて,山陰地域に適したおいしいサツマイモ栽培技術を開発しています。
![]()
![]()
![]()

城 惣吉 助教(農林生産学科)
土壌微生物の有用なはたらきを利用した作物の生産性向上に関する研究に取り組んでいます。特に,植物共生微生物の有用な機能の解明やその利用技術の確立を目指しています。
![]()
![]()

宋 相憲 助教(農林生産学科)
ミールワームの飼料となる未利用資源を探索し,生産方法を開発するとともに,生産されたミールワームを用いた食品,飼料加工などの活用に関する研究を行っています。
![]()
![]()
![]()
![]()

石井 将幸 教授(環境共生科学科)
水源と田畑をつなぐ用水路。水にはエンジンもブレーキもないので,用水路は緩い下り坂がずっと続くように引かれています。この難しい設計作業をAIにさせてみようと悪戦苦闘しています。
![]()

谷野 章 教授(環境共生科学科)
太陽電池パネルの下で植物がどのように育つかについて研究しています。気候変動,食料と人口の偏在,エネルギー資源転換が一斉に進行するためにこのような研究が必要です。
![]()

上野 和広 准教授(環境共生科学科)
安定的な食料生産を支える農業水利施設を長期間に渡って大切に使用するため,その老朽化の原因や補修・補強対策に関する研究を進めています。
![]()

劉 佳啓 准教授(環境共生科学科)
農作物の生育評価技術として、地上部に対応した可移動式フェノタイピング測量装置と、地下部に対応した地中レーダーによる根菜類の非破壊測定手法を開発しています。スマート農業への応用を目指しています。
![]()
![]()
![]()

李 治 助教(環境共生科学科)
環境負荷を低減させ,持続可能な農業を実現するために,作物の栽培と電力の生産が同時にできる営農型太陽光発電システムについて研究しています。
![]()
![]()
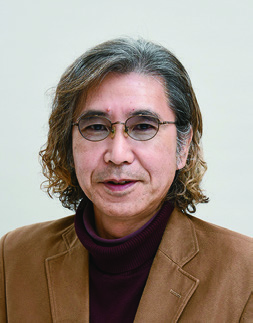
松本 眞悟 教授(附属生物資源教育研究センター)
土壌中の有害重金属の動態を解析するとともに,植物によるその吸収・排除機構を明らかにすることで安全な農産物の生産ならびに汚染土壌の浄化を研究しています。
![]()
![]()
![]()
![]()
<病害虫防除>

塩月 孝博 教授(生命科学科)
安定的な農作物生産を行うために必要な病害虫防除について,抵抗性を持つ害虫にも効果を示し,害虫以外の昆虫には影響の少ない制御剤の開発のための研究を行っています。
![]()
![]()

池田 泉 准教授(生命科学科)
病害虫に選択的に作用する薬剤を開発するため,その作用点となる神経伝達物質受容体に特異的に作用する新規化合物の合成と生物活性を評価する研究を行っています。
![]()
![]()
![]()

上野 誠 教授(環境共生科学科)
農作物の安定供給に貢献するために,「生きた微生物」や「微生物・植物が生産する天然物質」による植物の病気の防除とそのメカニズム解明に関する研究を進めています。
![]()

木原 淳一 教授(環境共生科学科)
道端でよく見かけるイネ科植物のコバンソウ類に発生する葉枯性病害について,病原菌の分離・同定・病原性・生活環などに関する研究を行なっています。
![]()
![]()

泉 洋平 准教授(環境共生科学科)
農作物の安定的な供給に必須である病害虫防除について,「未熟果実から揮散される匂いによる餌探索の撹乱」など,昆虫の生態を利用した防除法を研究しています。
![]()
![]()

児玉 基一朗 特任教授(先鋭研究部門)
微生物を利用した環境に優しい病害防除法(バイオコントロール)の開発と現場への応用について、国際共同研究(バナナ病害)を進めています。
![]()
![]()
<遺伝資源>

荒西 太士 教授(生命科学科)
ミトゲノムの比較解析により日本在来のドジョウ希少種の系統進化と分岐分類を査定しています。
![]()
![]()
![]()

丸田 隆典 教授(生命科学科)
植物の環境順応機構の理解を深め,植物バイオテクノロジーに応用するため,ストレス耐性や細胞死に関わる遺伝子の同定と機能解析を行っています。
![]()
![]()
![]()
![]()

古水 千尋 准教授(生命科学科)
多様な陸上植物の遺伝情報を比較することで、有望な遺伝資源の候補を見つけることを目指しています。
https://www.ipc.shimane-u.ac.jp/evobio/
![]()
![]()
![]()
![]()

須貝 杏子 助教(生命科学科)
絶滅危惧種がもつ遺伝的多様性や集団の固有性を調べています。見た目の数だけではなく,遺伝的多様性を守る方法を提案します。
![]()

江角 智也 教授(農林生産学科)
幼樹開花するサクラの研究から,十年以上かかる果樹の育種期間を劇的に短縮する方法を開発します。モモクリ3年カキ8年...を何でも1年に!
![]()
![]()
![]()

小林 伸雄 教授(農林生産学科)
ツツジ,トウテイラン,ハマダイコン,ナバナなどの地域特産植物遺伝資源の特性を評価し,品種改良や地域活性化に活用する研究を展開しています。
![]()
![]()

田中 秀幸 准教授(農林生産学科)
大学附属農場で保存管理されている約160品種のサクラ遺伝資源を活用し,「サクラの周年開花技術」や「効率的な増殖法」の開発に関する研究を行っています。
![]()
![]()

中務 明 准教授(農林生産学科)
品種改良に応用するため,鑑賞植物がもつ多様な花色・花形が,野生個体や栽培品種からどのように変化したかを解析しています。
![]()
![]()

加古 哲也 助教(農林生産学科)
地域が有する遺伝資源について、育種や生産技術の開発を通じた活用方法について研究を行っています。
![]()
![]()

吉田 真明 教授(附属生物資源教育研究センター)
環境DNA手法をつかった共同研究から,日本全国の沿岸のお魚マップを作っています。DNAデータに基づいた生物の分布パターンを調べて,生物資源の利用に繋げます。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

児玉 基一朗 特任教授(先鋭研究部門)
それぞれの地域に特徴的な素材(果樹・花・樹木)に由来するローカル発酵微生物(酵母、乳酸菌など)を活用した、新しい発酵製品開発による地域活性化に取り組んでいます。
![]()
![]()
<森林>

吉村 哲彦 教授(農林生産学科)
木材生産・林業機械・林道計画・作業システム・林業経営・森林測量・環境教育・ツーリズム・森林景観・公園・緑地・登山・アウトドア活動・キャンプなどの研究を行っています。
![]()
![]()

髙橋 絵里奈 准教授(農林生産学科)
健全な森を増やしたいと思い,木材生産を目指してたくさん苗木が植えられた人工林のスギやヒノキの管理について研究しています。
スギやヒノキの人工林で健全な森をつくり,木材生産に役立つために「いつ」「どこを」「どれだけ」伐ればよいかという間伐の研究をしています。
![]()
![]()

米 康充 准教授(農林生産学科)
人工衛星・航空機・ドローンの画像やレーザの測量技術を利用して森林の資源量や地形を計測します。これを基に環境や防災に配慮した森林の計画を行います。
![]()
![]()
![]()

久保 満佐子 准教授(環境共生科学科)
森林の骨格となる樹木は数百年を生きます。種子から発芽し成長し枯死するまでの樹木の生活史と,長い時間をかけて変化する森林の動態について研究しています。
![]()

橋本 哲 准教授(環境共生科学科)
山地森林流域への降雨や降雪の蒸発過程を流出過程を予測するモデルを開発し,水源流域森林の水資源に対する機能評価を検討する研究をしています。
![]()
![]()

清水 加耶 助教(環境共生科学科)
東南アジアの熱帯雨林に生息する昆虫が植物や他の動物類とどのように関わりながら群集を構成しているのかを研究しています。
![]()

藤巻 玲路 助教(環境共生科学科)
森林の植物と土壌との間での炭素や窒素の動態を研究しています。炭素・窒素動態は森林の生産力に影響すると同時に,炭素隔離や水質浄化といった森林の生態系サービスとも強く関係しています。
![]()
![]()

山下 多聞 准教授(附属生物資源教育研究センター)
森林生態系における物質循環をメインテーマとし,とくに森林土壌を対象に温室効果ガスの収支および炭素窒素重金属の収支の解明に取り組んでいます。
![]()
![]()
![]()
![]()
<土壌>

桑原 智之 教授(環境共生科学科)
地下水や温泉排水に含まれる希薄なフッ素やヒ素などの有害イオンを除去するため,金属元素を組み合わせた複合含水酸化物による新規の水処理用吸着剤を開発しています。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
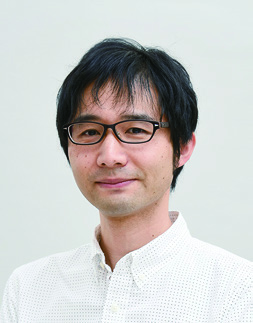
佐藤 邦明 准教授(環境共生科学科)
土壌生態系が持つ環境浄化機能を利用した水質浄化技術の開発を目的に,生物模倣技術を取り入れながら最適な土壌構造の検討を行っています。
![]()
![]()
![]()

巣山 弘介 准教授(環境共生科学科)
よく「農薬を使うと土が死ぬ」と言われますが,本当にそうなのか? 単なる「思い込み」ではないのか? そのような疑問を持った私は,それを科学的に評価する研究を行なっています。
![]()

劉 佳啓 准教授(環境共生科学科)
UAV写真測量やLiDAR計測を用いて、砂丘農地における風食・堆積の空間分布を高精度に可視化し、土壌侵食の動態把握と保全対策に活用しています。
![]()
![]()
![]()

木原 康孝 講師(環境共生科学科)
環境問題の扇の要とも言われる土壌の中で水,物質,熱,気体がどのように移動しているかを流域規模から実験室まで様々なレベルで研究を進めています。
![]()
![]()
![]()
![]()

藤巻 玲路 助教(環境共生科学科)
土壌に生息する動物の働きについて研究しています。ミミズやヤスデなどの大型土壌動物は,土壌の構造を変えることで他の生物に影響し,土の肥沃度を改善します。
![]()

深田 耕太郎 助教(環境共生科学科)
物理的な視点から土壌を調べる方法を探索しています。例えば,土が乾く現象を,電気の性質を利用して調べています。
![]()
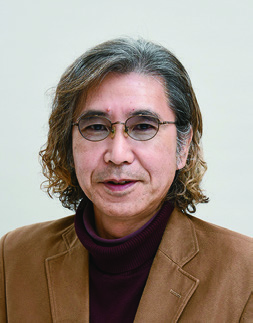
松本 眞悟 教授(附属生物資源教育研究センター)
土壌中の有害重金属の動態を解析するとともに,植物によるその吸収・排除機構を明らかにすることで安全な農産物の生産ならびに汚染土壌の浄化を研究しています。
![]()
![]()
![]()
![]()
<水循環・物質循環>

武田 育郎 教授(環境共生科学科)
宍道湖に流れ込む最大の河川である斐伊川について,窒素やリンなどの水質を調査し,人口減少であるにもかかわらず,あまり水質が良くならない原因などを考えています。
![]()
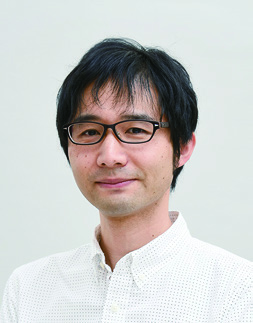
佐藤 邦明 准教授(環境共生科学科)
ヨシやタケ等の有機性の地域未利用資源を炭化する等して,土壌改良資材や環境浄化資材として有効利用する研究を進めています。
![]()
![]()
![]()

佐藤 裕和 准教授(環境共生科学科)
洪水の氾濫とともに氾濫する物質(土砂や流木,ゴミ)の制御による水害の軽減,海岸侵食を念頭に置いた流砂系の土砂循環について河川工学の立場から検討しています。
![]()
![]()

橋本 哲 准教授(環境共生科学科)
山地森林小流域で観測を行い,渓流水流量,蒸発散量の季節変化,渓流水の水温などを年間を通じて予測するモデルを開発しています。
![]()
![]()

長門 豪 准教授(環境共生科学科)
私は,環境中の汚染物質がどのように変化するかについて研究しています。特に現在は,プラスチックと多環芳香族炭化水素の環境中での変化について注目しています。
![]()
![]()

藤巻 玲路 助教(環境共生科学科)
森林の水源涵養機能に関して,雨水が樹木-土壌-渓流へと流れてゆく際の水質の変化を研究しています。これは,森林が持つ水質浄化の生態系サービスを強化する管理手法の開発にも繋がります。
![]()
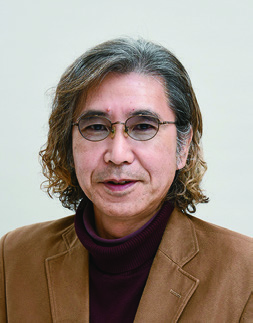
松本 眞悟 教授(附属生物資源教育研究センター)
土壌中の有害重金属の動態を解析するとともに,植物によるその吸収・排除機構を明らかにすることで安全な農産物の生産ならびに汚染土壌の浄化を研究しています。
![]()
![]()
![]()
![]()
<防災・減災>

米 康充 准教授(農林生産学科)
台風時の風の流れのコンピュータシミュレーションと森林の状態から,樹木が倒壊するプロセスを解明して,台風に負けない森林つくりを目指します。
![]()
![]()
![]()
![]()

上野 和広 准教授(環境共生科学科)
災害時においても農村地域の安全性を確保するため,また,食料生産を継続できるようにするため,農業水利施設を対象とした防災・減災対策に関する研究を進めています。
![]()

佐藤 裕和 准教授(環境共生科学科)
水害の減災について,地域性,地理性,歴史性を尊重しながら実現可能な具体策を模索しています。計算や実験など研究のアプローチは様々ありますが,「川歩き」が基本です。
![]()
![]()

劉 佳啓 准教授(環境共生科学科)
飛砂被害軽減のため、砂丘地に設置された堆砂垣や静砂垣の防砂効果をドローンと三次元解析手法を用いて定量的に評価し、防災インフラ整備に貢献しています。
![]()
![]()
![]()

佐藤 真理 助教(環境共生科学科)
降雨や浸透により土構造物が被災して損傷することが問題となっています。実験や解析,現地調査を組み合わせて,そのような問題を解決するための研究を進めています。
![]()
<経済・地理・歴史・文化>

小林 伸雄 教授(農林生産学科)
日本の伝統園芸文化が生み出したツツジ園芸品種の起源解明や国内外への伝搬に関する研究を行っています。
![]()
![]()

森 佳子 准教授(農林生産学科)
金融はどのようにして農業の成長産業化に貢献できるのか,という観点から,様々なタイプの農業経営に対する金融機関の役割について研究を行っています。
![]()
![]()
![]()

保永 展利 准教授(農林生産学科)
条件不利地域の特性が地域の経済発展や農地保全に及ぼす影響,地域産食品の消費者嗜好などを研究しています。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

米 康充 准教授(農林生産学科)
航空機・ドローンのレーザ測量技術を利用して樹木で覆われた地面を計測し,そのデータとAIを用いて,森林に埋もれた古墳や遺構をたくさん見つけます。
![]()
![]()

中間 由紀子 准教授(農林生産学科)
戦後日本において農業政策が実際にどのように行われ,農村地域の人々にどのような影響を及ぼしたのかについて,資料や聞き取りをもとに研究を行っています。
![]()
![]()

Rosalia Natalia Seleky(ロサリア ナタリア セレキー) 助教(農林生産学科)
インドネシア及び日本の農業後継者の課題・集落営農の発展と地域農業・農村振興・アグリバイオビジネス・食料消費・農業経営などの研究を行っています。
![]()
![]()

末永 千絵 助教(農林生産学科)
農産物・食品流通の仕組みについて、情報通信技術(ICT)、電子商取引(EC)の活用に着目し研究しています。
![]()
![]()

桑原 智之 教授(環境共生科学科)
中海の干拓事業で生じた湖底の土砂採取跡(浚渫窪地)の貧酸素環境を改善するため,地元の認定NPOや企業・行政と協働して環境修復事業や調査研究を行っています。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

久保 満佐子 准教授(環境共生科学科)
日本の原信仰として巨木や森などの自然信仰があります。現在はご神木や社叢林として存在するものもあり,それらの分布や状態について研究しています。
![]()

佐藤 裕和 准教授(環境共生科学科)
河川工学的な意味付けが薄弱であった国指定名勝・錦帯橋の橋脚の謎について,歴史的な経緯を踏まえながら検証してきました。河川文化財の研究を拡張したいと考えています。
![]()